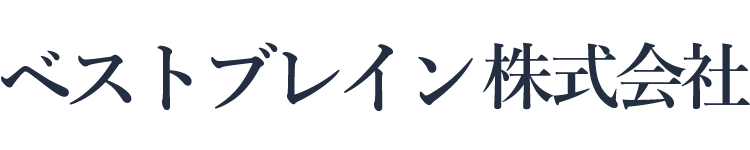| № | 問題 |
| 1 |
以下は、クレームを付けた顧客の感情を刺激する言葉遣いであるが、妥当でないものはどれか。*正解はひとつです。 #1 「はい。はい。」と「はい。」を連呼する。たとえ不貞腐れた態度ではなく、真摯な態度で連呼したとしても、「『はい』と返事をしていれば済むと思っているのか、しっかり聞いているのか」という疑念を生むおそれがある。 #2 「うーん」と言って考え込む。「うーん」は、そもそもお客様に対する言葉ではない。また、返答に窮し困惑した表情を見せることも、悪意がある相手に付け込まれる隙となる。 #3 「先ほども申し上げましたが・・・」は、理解力の乏しい相手あるいは対応者の説明に納得せず、クレームの理由を執拗に指摘し要求を重ねる相手には効果的である。 #4 「ですが」、「ですから」は、相手をバカにした、あるいは相手の言い分を否定したととらえることができる。 2025年1月号 |
| 2 |
以下は、ハラスメントに関する記述であるが、妥当なものはどれか。*正解はひとつです。 #1 セクハラは、それを受けた相手の主観で成立すると考えることは、セクハラを防止する上で妥当でない。 #2 カスハラによって社員がダメージを受けることを予防し、あるいはダメージを最小化するために最も大切なことは、カスハラであることを速やかに認定し、毅然とした態度での対応を講じることである。 #3 上司から声をかけられても無視するなど、部下による上司に対する嫌がらせはパワハラとはいえない。 #4 パワハラとは異なり職場の優越的地位に基づかないモラハラも懲戒処分の対象となり得る。このモラハラの定義は厚生労働省も明らかにしている。 2024年12月号 |
| 3 |
以下は、東京商工リサーチが公表したカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます)に関するアンケートの結果であるが、誤りはどれか。*正解はひとつです。 #1 対策を講じていない企業が7割超あった。一方、講じた対策のトップ3は、研修、相談窓口の設置または対応方針の策定であった。 #2 大企業よりも中小企業の方がカスハラを受けやすい傾向が明らかになった。また、休職や退職に追い込まれる件数も中小企業の方が多かった。 #3 カスハラを受ける業種は、宿泊業、飲食業、道路旅客運送業がトップ3であった。ただし、最も多く休職等が発生したのは、窯業・土石製品製造業であった。 #4 カスハラの内容で、過半数を超えたものは攻撃的・威圧的な口調、長時間の対応であった。一方、暴力、録音・録画はいずれも5%未満であった。 2024年11月号 |
| 4 |
以下は、クレーム対応に関する記述であるが、正しいものはどれか。*正解はひとつです。 #1 クレームを付けた相手の法外な要求に対して「わかりました」と答えることは、その要求を受け入れることの表明であり、万が一やり取りが録音等されていれば致命的な失言と言える。 #2 感情的にクレームを付ける相手に「不快な思いをさせて申し訳ありません」などと謝罪することは、非を認めることになるほか相手を増長させるだけで収束に貢献しない。 #3 クレームに関する説明と謝罪で同席した部下に「君も謝りなさい」などと謝罪を促すことはパワハラになるおそれがある。 #4 「炎上するぞ!」「訴えるぞ!」といった恫喝にも感じる発言に、「仕方ありません」と答えることは、非を認めたものと相手が理解するので禁句と言える。 2024年9月号 |
| 5 |
以下は、厚労省マニュアルに記載されるカスタマーハラスメントに関する記述であるが正しいものはどれか。*正解はひとつです。 #1 カスタマーハラスメント対策に取り組むことについては、厚労省マニュアルが公表される以前(2020年)に厚生労働省が指針で言及している。 #2 カスタマーハラスメントの行為者には、商品の購入をしていない、あるいはサービス(役務)の提供を受けていない人物は含まれない。 #3 カスタマーハラスメントであるかどうかの判断基準は、要求内容が妥当性を欠くこと、要求実現の手段が相当性を欠くこと、この両方に該当する必要がある。 #4 カスタマーハラスメントへの対応は難しいため、その対応を一般従業員に習得させるよりも、相談窓口の設置・運用に注力すべきである。 2024年4月号 |
| 6 |
以下は、カスタマーハラスメントに関する記述であるが正しいものはどれか。注)正解はひとつです。 #1 商品に瑕疵等が認められないにもかかわらず、瑕疵があると思い込んでのクレームは、その手段が常識的なものである限りカスタマーハラスメントとはいえない。 #2 顧客と接客中にトラブルになった店舗スタッフは、会社側に労働者の身体等の安全を確保しつつ労働できるような配慮を欠いたとして損害賠償を求めることができない。 #3 従業員から相談を受ける相談対応体制の整備は、対策の基本的な枠組みのひとつであるが、この相談対応者はクレーム対応に相応の知見を有する社員が適任であり、相談者の上司とすることは妥当ではない。 #4 従業員への性的な言動に対しては、録画・録音により証拠を確保することになるが、この録音・録画に当たっては相手の許可を得る必要はない。 2024年3月号 |