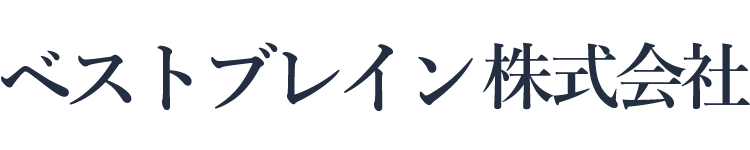| № | 問題 |
|
1 |
問 改正道路交通法(2026年施行予定)に関する以下の記述のうち正しいものはどれか。 *正解はひとつです。 #1 これまでは規制のない一般道路の最高速度は時速60キロであったが、改正により時速30キロになる。 #2 自転車の信号無視等も反則切符(交通反則告知書)の対象となる。ただし、違反者は12歳以上(中学生以上)である。 #3 自動車を運転し自転車を追い越す場合は、1.5メートルの間隔をあけるか、その間隔を確保できない場合は徐行して追い越すことになる。 #4 改正前は自転車の酒気帯び運転またはその違反者に酒を提供する行為には罰則がなかったが、改正により罰則が課せられる。 |
|
2 |
問 以下の記述のうち誤りはどれか。 *正解はひとつです。 #1 ランサムウェアに関する専門的な知識や技術のない人物による被害が拡大しているといわれている。その背景にはランサムウェアのビジネスモデル化があると指摘する向きがある。 #2 感染経路は、フィッシングメール、改ざんされたWebサイトからのダウンロードあるいは脆弱なリモートデスクトップなどである。 #3 感染のサインには、「ファイルの拡張子が突然変わる」、「ファイルを開こうとするとエラーになる」がある。 #4 感染のサインに遭遇した場合(感染の疑いを感じた場合)は、ネットワークから直ちに切り離し、シャットダウンする、またはPCを初期化する。 2025年10月 |
|
3
|
問 女性の防犯に関する以下の記述のうち正しいものはどれか。 *正解はひとつです。 #1 電車内での痴漢被害に遭いにくいとされる場所には、電車の出入り口付近がある。 #2 エレベーターの箱内で操作パネルに向き合って立つと背後が無防備になりやすいので、操作パネルの直近に位置することは避ける方が無難である。 #3 警視庁は、デジポリスという防犯アプリを提供しているが、これは警視庁の管轄内=東京都内でしか使えない。 #4 性的被害が発生しやすい場所の傾向として、不同意性交が発生する場所は中高層住宅が最多で、不同意わいせつは路上が最多である。 *設問、解説にジェンダー差別という問題を生じさせないための取組みには、ChayGPTの活用も含まれています。 |
| 4 |
以下は、生成AIの活用に伴うリスクに関する用語の説明であるが、誤りはどれか。*ここでは、リスクをネガティブな可能性として使います。*正解はひとつです。 #1 プロンプトインジェクションとは、ユーザーが悪意をもって入力し、あるいは悪意はないものの誤った入力により意図しない動作や結果を引き起こしてしまうリスクをいう。 #2 ハルシネーションとは、事実に反する内容をもっともらしく生成してしまうリスクをいう。 # 3フィルターバブルとは、差別的な情報など偏った情報を出力するリスクがある仕組みといえる。 #4 エコーチェンバーとは、差別的な情報など偏った情報が出力されてしまう現象をいう。 2025年7月 |
|
5 |
問 以下は、日本郵便の不適切な点呼の原因・問題として指摘された第一線の実態に関する記述であるが、誤りはどれか。*正解はひとつです。 #1 点呼を実施していないにもかかわらず点呼記録簿は作成しておくという行為が行われていた。 #2 点呼記録簿等の確認に加え、実際に現場で点呼が適正に行われているかのモニタリングは行われていなかった。 #3 “勤務中に飲酒をするはずがないという認識”あるいは“そもそも飲酒しない社員にアルコール検査は不要”という認識を改めるための取組みは行われていなかった。 #4 点呼の実施方法を明らかにするマニュアルは、運用されていない現場が複数あったばかりか、内容の誤ったマニュアルまでがあった。 |
|
6
|
以下は、東京商工リサーチが公表したカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます)に関するアンケートの結果であるが、誤りはどれか。*正解はひとつです。 #1 対策を講じていない企業が7割超あった。一方、講じた対策のトップ3は、研修、相談窓口の設置または対応方針の策定であった。 #2 大企業よりも中小企業の方がカスハラを受けやすい傾向が明らかになった。また、休職や退職に追い込まれる件数も中小企業の方が多かった。 #3 カスハラを受ける業種は、宿泊業、飲食業、道路旅客運送業がトップ3であった。ただし、最も多く休職等が発生したのは、窯業・土石製品製造業であった。 #4 カスハラの内容で、過半数を超えたものは攻撃的・威圧的な口調、長時間の対応であった。一方、暴力、録音・録画はいずれも5%未満であった。 2024年11月号 |
| 7 |
次は、障害者差別解消法に定める“合理的配慮”あるいは“不当な差別的取扱いの禁止”に関する記述であるが、妥当なものはどれか。*正解はひとつです。 #1 合理的配慮または不当な差別的取扱いの禁止の対象となる障害者は、障害者手帳を持つ方に限られる。またこの法律で合理的配慮等の義務を負う事業者には、営利を追求しないボランティアも含まれる。 #2 正当な理由があれば、不当な差別的扱いとはいえないが、ここにいう正当な理由には、「前例がない」は含まれないが「常識的に無理である」は含まれる。 #3 聴覚に障害を持つ方からの宿泊予約の申し込みを、「万が一火災が起きた場合、火災警報が聞こえずに避難が遅れるかもしれない。安全を保障できない」という理由でお断りをした。これも正当な理由といえる。 #4 障害のある方が希望するサービスを提供するために、他のお客様から見て明らかに特別扱いすることは、不当な差別的取扱いとはいえない。 2024年5月号 |
| 8 |
以下は、今般整備された撮影罪と従来の迷惑防止条例違反に該当する盗撮に関する記述であるが、誤りはどれか。*誤りはふたつあります。 #1 撮影罪も盗撮も現行犯逮捕はできる。しかし、現行犯逮捕ができない状況では、両者ともにあらかじめ用意された逮捕状がなければ逮捕はできない。 #2 撮影罪は実名報道されるおそれが、迷惑防止条例違反よりも大きいといえる。 #3 撮影罪は、勾留(逮捕・留置に引き続く強制的な身柄拘束、最長20日間)される可能性が大きいといえる。 #4 撮影罪も盗撮も未遂であれば、処罰の対象とならない。 2023年10月号 |
| 9 |
以下の記述で誤りはどれか。*正解はひとつです。 #1 今年、急速に拡大が見られた 「Emotet」について、パスワード付きのZIPファイルをメールで送信する手口が発見された。この手口は、ウイルス対策のソフトによる検知をすり抜ける性質が指摘された。 #2 ランサムウェアあるいはダブルエクストーション(二重恐喝)のソフトは、入手が難しいものではなく、今や闇サイトで購入できる。 #3 インターネットを利用する詐欺などのサイバー犯罪の検挙件数は、増加傾向にあるなか、例年一定の検挙件数を計上する不正アクセス禁止法違反の検挙件数も前年に比べ急増した。 #4 サイバー空間での犯罪のうち検挙件数の最多は、詐欺または不正アクセスではなく児童ポルノ禁止法違反であり、他の検挙罪名(違反)に比して突出している。この事実は業務外の非行の防止という点からも注意したい。 2022年9月号 |
| 10 |
以下は、公益通報者保護法(以下、「法」と記します)に定める通報者の保護に関するやり取りであるが、誤っているものはどれか。*正解はひとつです。 #1 同僚から「役員Xに公職選挙法違反の疑い(刑罰あり)があるので、通報を考えている。役員Xの反感を買って人事的な報復を受けるおそれはあるが、法により保護されるはずだ」と明かされたので、「法による保護は受けられない」と答えた。 #2 同僚から「上司Zから食事の誘いをたびたび受けている。Zをセクハラの行為者として通報したいが、通報したら処遇面で嫌がらせされるかも知れない。法による保護は受けられるか」と相談されたので、「法による保護は受けられないと思う」と答えた。 #3 「かつて派遣で働いていた際に知り得た問題が公益通報の対象になることを確認したので通報を考えている。派遣期間が終わり半年経過したが法による保護は受けられるか」と明かされたので「法による保護は受けられる」と答えた。 #4 同僚から「公益通報であれば事業者は損害賠償を請求できないのか」と聞かれたので「改正前から損害賠償請求はできないと明文で定められていた」と答えた。 2022年5月号 |